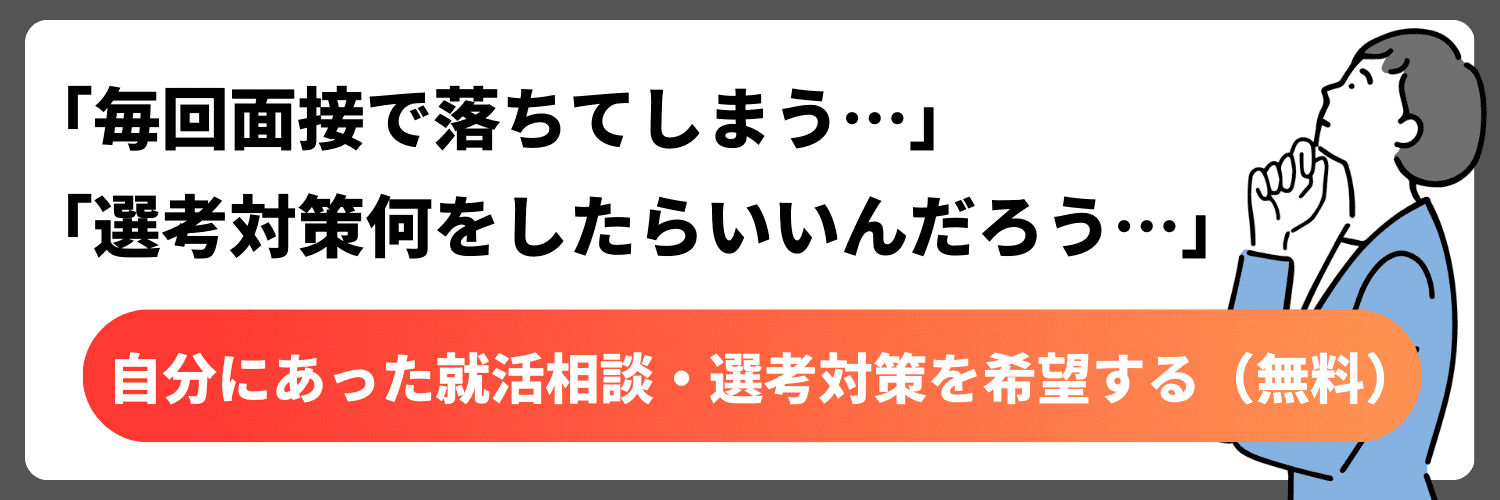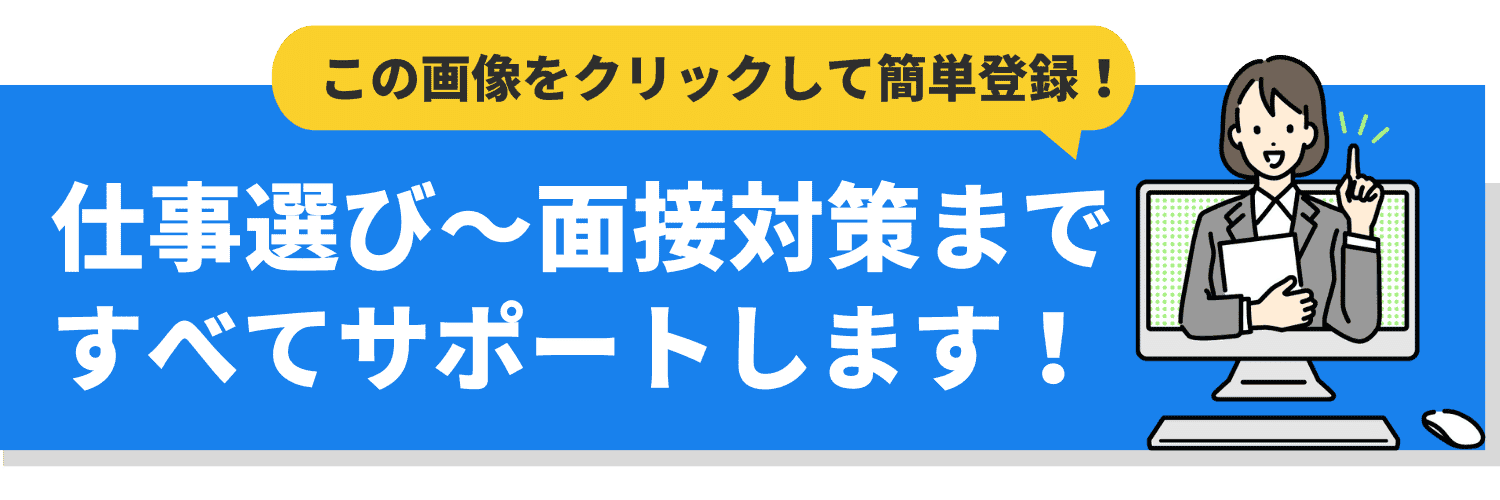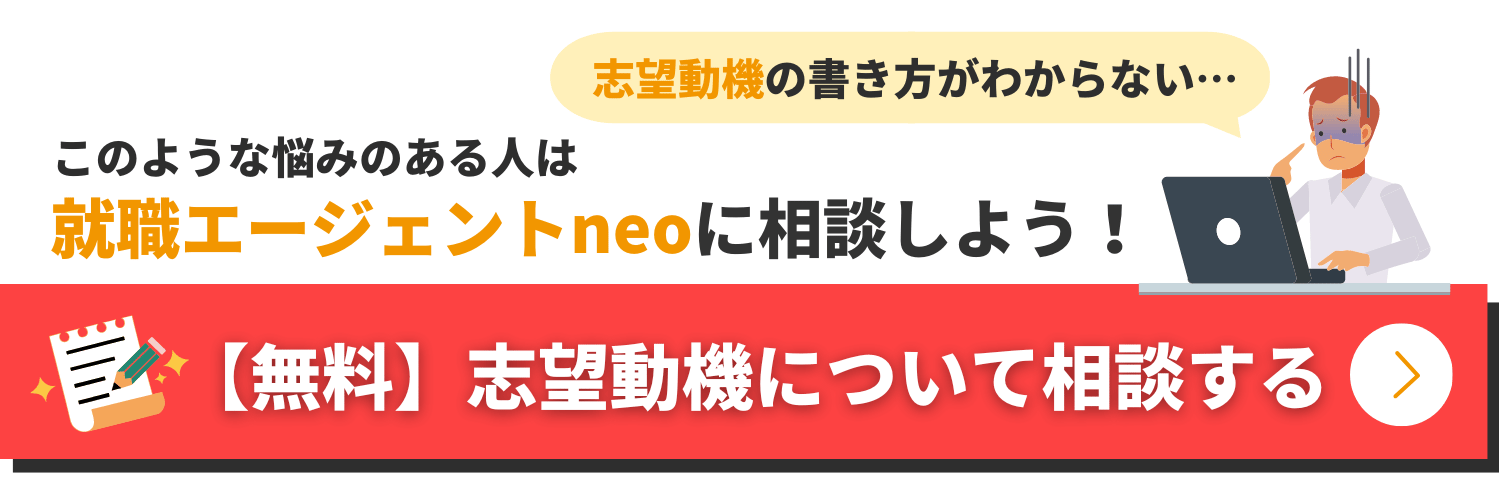●志望動機を書く際には、「保育士になりたい理由」「園を選んだ理由」「入社(入職)後のイメージ」を伝えると良い
●「どの園でも使える内容を書く」ことや「福利厚生などの待遇面を理由にする」ことはネガティブな印象を与えるため避けた方が良い
「保育士の志望動機の書き方がわからない」と悩んでいる就活生もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、保育士の志望動機で採用担当者が見ている点や志望動機を書く際のポイント、注意すべき点、志望動機を書くための事前準備などについて詳しく解説しています。
例文も掲載していますので、志望動機の書き方がわからない就活生は是非参考にしてみてください。
保育士の志望動機で採用担当者が見ているポイント
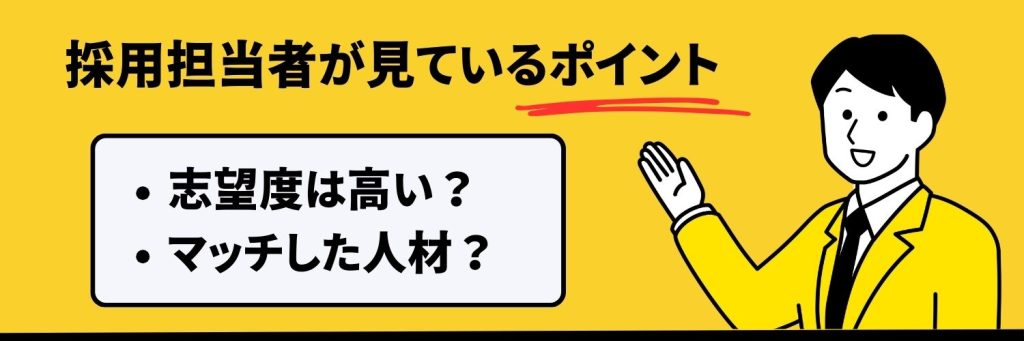
志望動機とは「応募した園で働きたい理由」のことをいい、採用担当者が重要視する項目の1つです。
そこで本章では、採用担当者が志望動機でチェックしているポイントについて確認していきましょう。
自園への志望度は高いか?
まず1つ目に、「自園への志望度」を確認しています。採用担当者としては、自園に入社したい意欲が強く、かつ自園で活躍してくれる人を採用したいと考えています。
そこで志望動機に書かれている内容を確認することによって、自園への熱意や入社意欲の高さを図ろうとしているのです。
自園にマッチした人材かどうか?
2つ目は「自園にマッチした人材かどうか」という点です。入れ替わりの激しい保育業界ですが、採用担当者としてはできれば長く働いて欲しいというのが本音です。
そこで、志望動機を通じて、自園が求めているスキルに合致しているのか、社風や職場の先輩社員とのなじめる人柄であるかについてもチェックしており、新卒採用であっても即戦力として働いてくれる社員を採用しようとしています。
保育士の志望動機の書き方のポイント
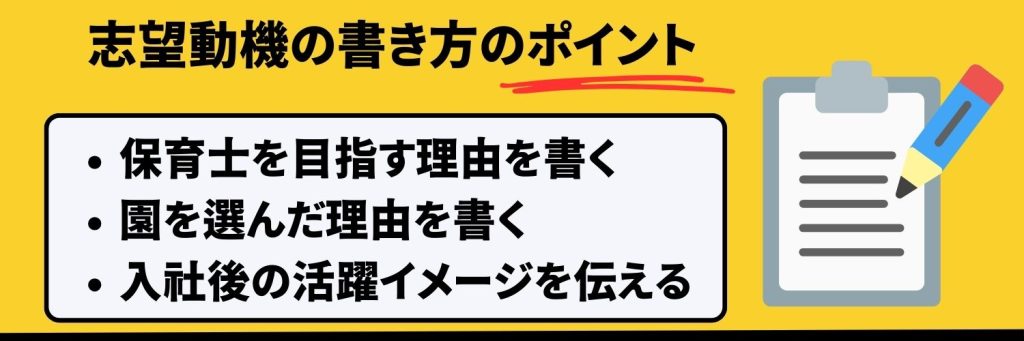
ここでは、保育士の志望動機の書き方のポイントをお伝えしていきます。志望動機を作成する際の参考にしてみてください。
なぜ保育士になろうと思ったのか
まずは、なぜ保育士になりたいのかを明確に伝えましょう。
例えば、「幼い頃にお世話になった保育士さんがとても良い先生で、毎日保育園に行くのを楽しみにしていました。私もこの先生のように子どもたち1人ひとりを大切にできる保育士になりたいと、憧れを持つようになりました」のように、具体的なエピソードを交えて伝えるとより信憑性のある内容となります。
なぜその園を選んだのか
保育士の就職先は、保育園以外にも病院や企業内の保育園、児童福祉施設など様々です。
その中でなぜ「保育園」を選んだのか、そして数ある保育園の中でなぜ志望園だったのかという理由を明確にしておきましょう。
例えば「保育園の理念である〇〇に共感してた」「保育見学時に行った際に子どもたちへの声かけの方法が印象的だった」などです。
この理由が明確であればあるほど、採用担当者からすると自園への熱意があり入社意欲が高いと感じるはずですので、思いを伝えるためにもこの点はしっかり深堀しておくことをおすすめします。
なかなか理由が浮かばないという人は、志望園のホームページを見る、実際に園を見学に行ってみるとより思いのこもった志望動機を作成することができるでしょう。
入社後のイメージを伝える
最後に採用担当者に自分を採用するとどのようなメリットがあるのかを伝え、入社後の働き方をイメージしてもらえるような内容を添えます。
具体的には、「クラブ活動で体力を鍛えてきたため体力には自信がある」や「明るい性格で、ハードな面があったとしても、それ以上に子どもが好き」という気持ちなどです。
その他にも、業務で必要になるピアノや歌が得意な人はこれらをアピールするというのも良いでしょう。
採用することによるメリットを入社後の業務で活かし、園に貢献していきたいという思いを伝えることで、より深みのある志望動機を作成することができます。
志望動機の書き方、考え方を詳しく知りたい人は下記をご覧ください。
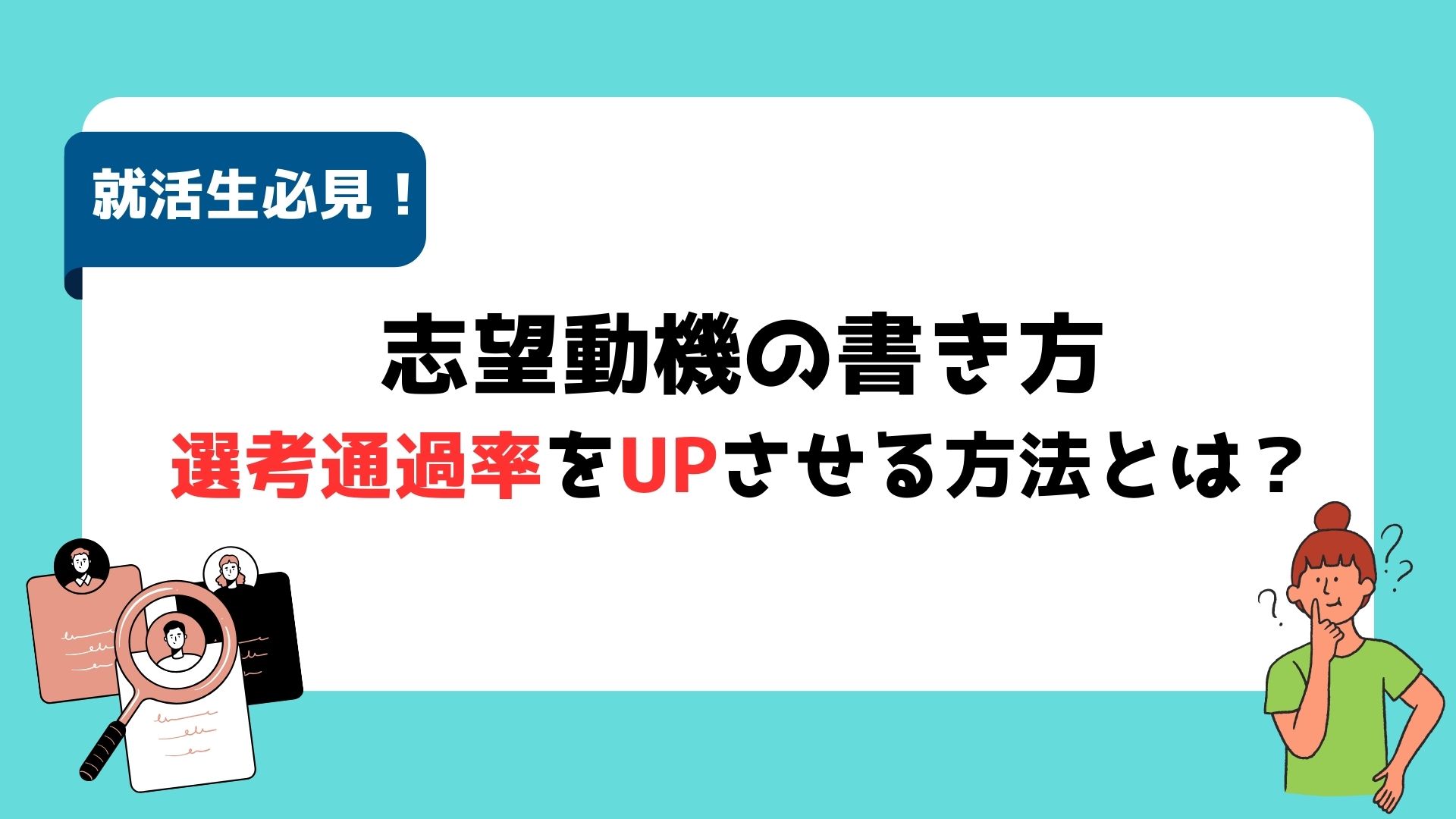
保育士の志望動機を書く際のNGポイント
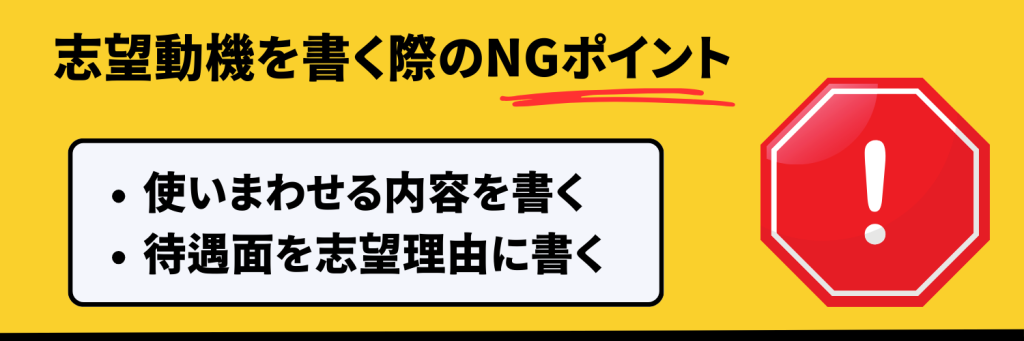
ここでは、志望動機を書く際に注意すべき点についてお伝えしていきますので、作成時の参考にしてみてください。
どの園にも使いまわせる内容を書く
就活をする際には複数の園にエントリーをすることが多いため、園別に志望動機を作成する作業は大変です。だからといって志望動機を使いまわすことはNGです。
冒頭でお伝えしている通り、採用担当者は「志望動機」を重要視しており、自園への熱意を感じるかどうかという点をチェックしています。
どこの園でも使えるような内容だと、「熱意が感じられない」「自園について全く興味がないのでは?」と思われ不採用となってしまうことが考えられますので、志望動機では必ず「志望園ならでは」の志望理由を考えるように意識をしましょう。
福利厚生などの待遇面を志望理由に書く
就職するのであれば出来る限り福利厚生が整っており、給料などの待遇の良い園が望ましいと考えることは当然です。
しかし、それを正直に伝えてしまうと、「待遇ばかりでうちの園のことを理解しているのか」と疑われてしまいかねません。
そのため志望動機には、待遇面ばかりを伝えるのではなく、志望園ならではの魅力や特徴を踏まえた内容を記載するよう意識をしましょう。
保育士の志望動機を書く前に準備すべきこと
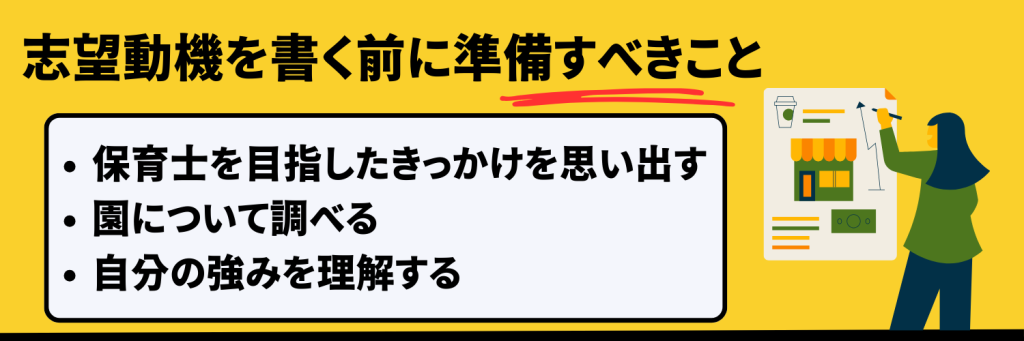
ここまで志望動機を書くポイントや注意点についてお伝えしていきました。ここでは、志望動機を書く前に用意をしておくべきことについてご紹介していきます。
保育士になろうと思ったきっかけを思い出す
まずはなぜ「保育士」になろうと考えているのかを改めて考えてみましょう。
「子供が好きだから」という漠然とした理由だけでなく、「なぜ子供が好きだと思うようになったのか」というきっかけや背景を考えていきます。
「なぜ?」「なぜ?」と深堀をしていくと保育士になろうと思った核心に気付くことができるはずです。
園について調べる
次に園についてしっかり調べてみましょう。前述の通り志望動機では「その園ならでは」の魅力や特徴に触れることで志望園への熱意を伝えることができます。
そのためにまずは徹底的に「志望園」について調べていくことが大切です。調べ方は「ホームページ」「口コミサイト」「保育士情報サイト」などを活用することをおすすめします。
園の雰囲気を一番理解するために最も良い方法は、直接自分の目で見て確かめることです。
どんな社員さんがいてどんな保育をしているのかなど見て感じた点、魅力に思った点などをまとめてみるとあなた独自の志望動機を見つけられるでしょう。
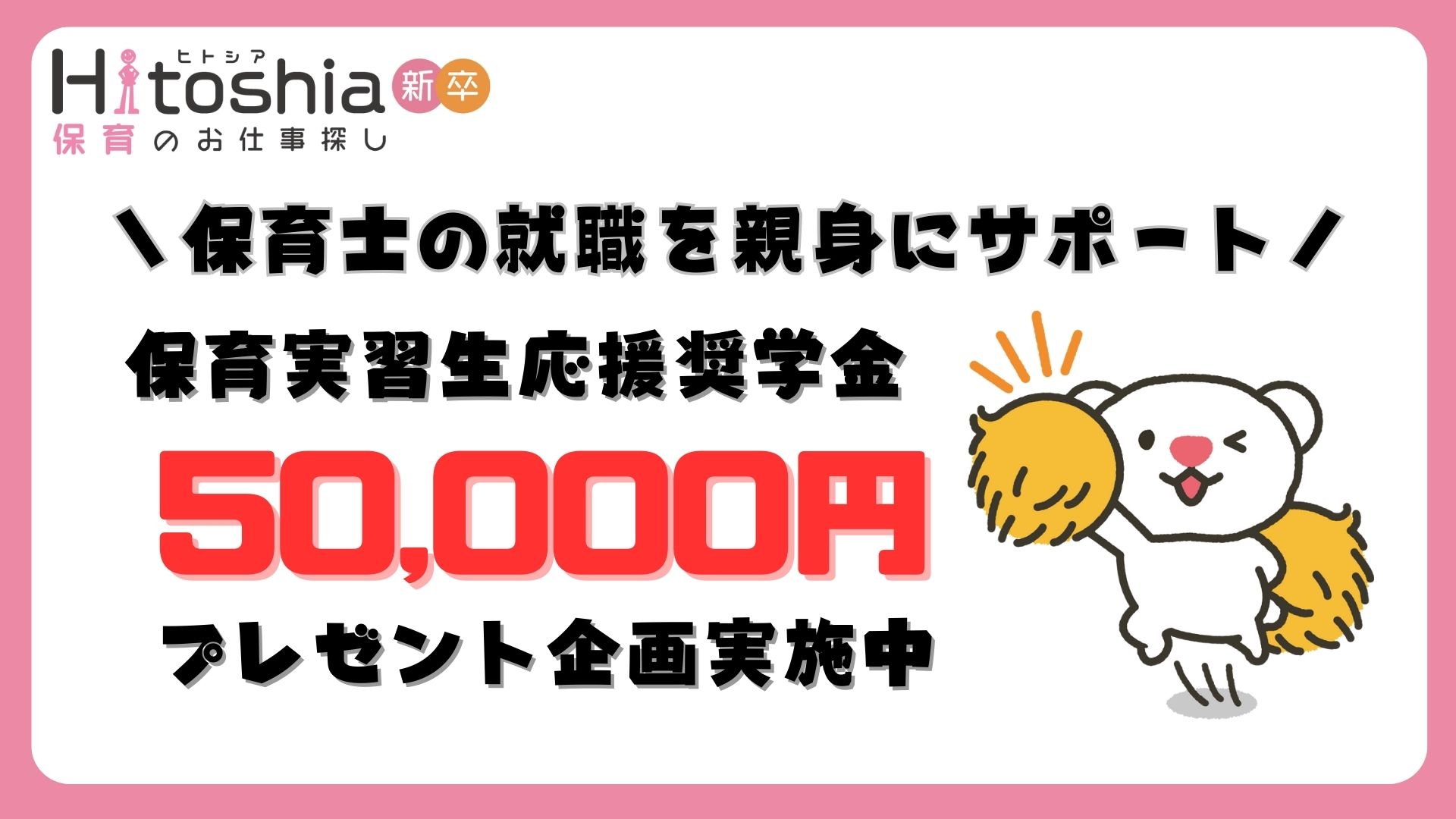
自分の強みを理解する
入社後の活躍をよりイメージしてもらうためにも自分の強みをアピールする必要があります。自分の強みは何か、自分の得意なことは何かを冷静に振り返ってみましょう。
ただし、自分の得意なことは「一輪車に乗ること」など、業務に活かすことが難しいものや志望園が求める人物像と合致しない強みでは逆アピールとなってしまう可能性が高いため注意が必要です。
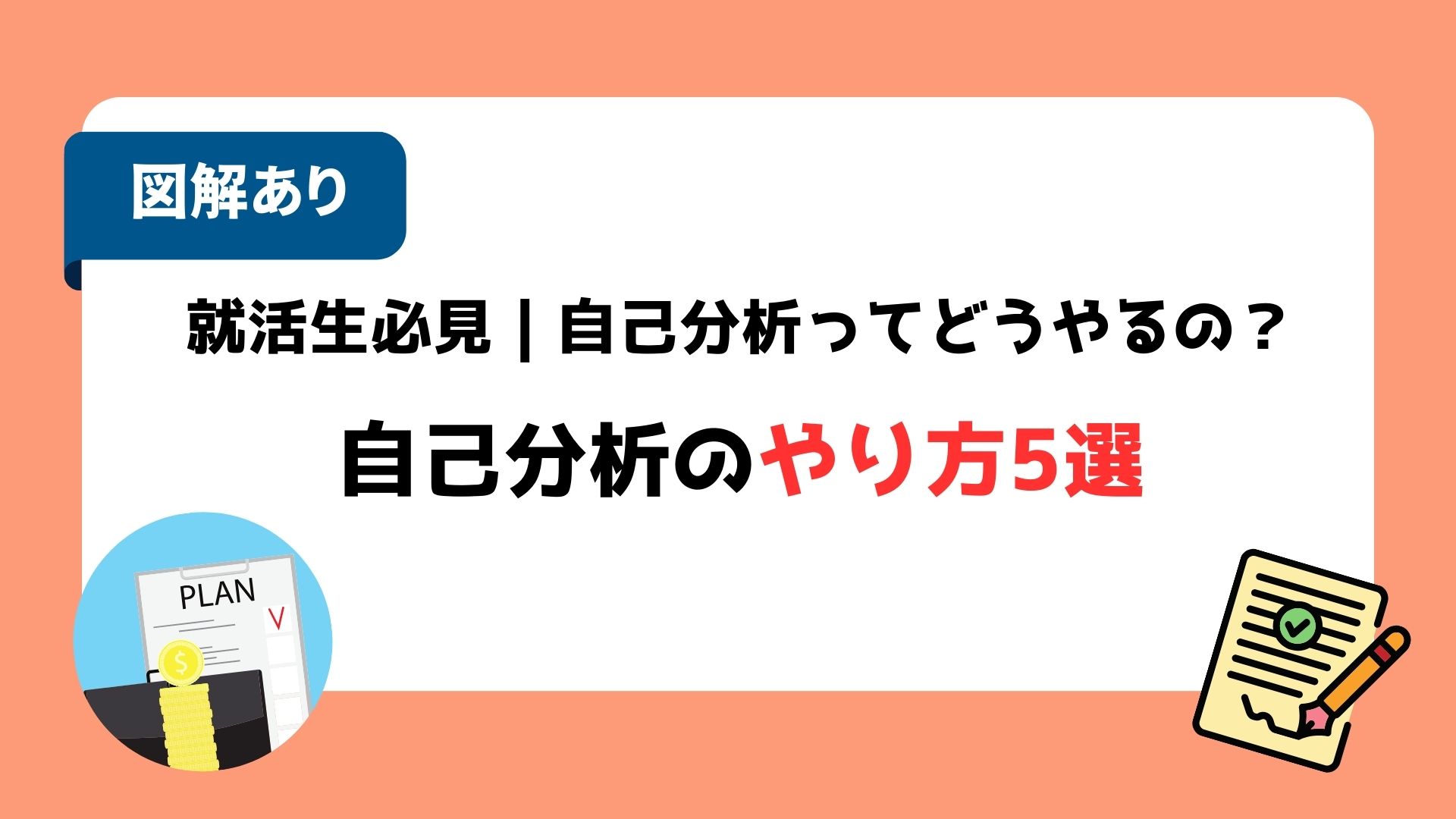
就活生にオススメの自己分析のやり方5つを図解と合わせて分かりやすく説明しています。
新卒保育士の志望動機の例文
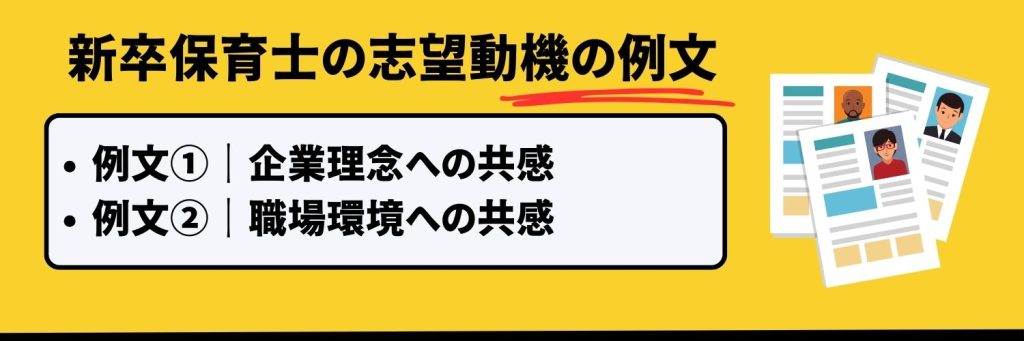
ここでは、新卒で保育士を目指す就活生に向けた志望動機の例文をご紹介していきますので是非参考にしてみてください。
保育士の志望動機例①|企業理念への共感
その理由は、自然と親しむ遊びを積極的に取り入れることで豊かな人間性を育もうとされている教育方針に共感したからです。
現代の子どもたちはバトルゲームなど、人と戦うゲームに熱中することで、人の痛みを感じにくくなっている傾向にあると私は危惧しています。
しかし同時に、子どもたちの健やかな心を育てることで、地域にとっての宝のような存在になってほしいと思っています。
そのため、貴園にて、自然との触れ合いを通して、思いやる心が育まれるように子どもたちに関わっていきたいと思います。私は、中学生時代からバレー部に所属して運動に親しんできました。
体力には自信がありますので、それを活かして、子どもたちの元気さに負けないようにしっかりお世話できる保育士になりたいと思います。
保育士の志望動機例②|職場環境への共感
私が貴園を志望した理由は、アットホームな雰囲気と社員同士の仲が良く温かい関係性が印象的だったからです。
仕事をする上で、従業員同士の連携と協力は、充実した保育環境を築く上で不可欠な要素であると考えています。
私は協調性とコミュニケーション能力に自信を持っており、円滑なチームワークの中で子どもたちが安心して成長できる場を提供できると確信しています。
また、私は小学生の頃から続けているピアノの経験を生かし、子どもたちに音楽を通じて豊かな経験を提供したいと考えています。音楽は感性やコミュニケーション能力を豊かにし、子どもたちの心の成長に寄与すると信じています。
そのため、貴園でのピアノ活動の導入やイベントでの活動など、様々な面で貢献していきたいと考えています。
貴園での保育スタッフとしての経験を通じ、子どもたちが笑顔で安心して成長できる場を共に築いていけるよう尽力していきたいです。どうぞ宜しくお願い致します。
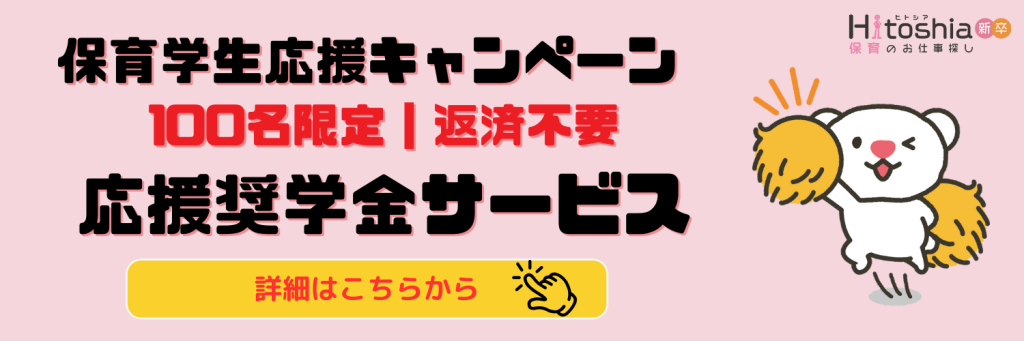
グーグルフォームに遷移しますので、詳細を知りたい方はフォームよりお問合せください。
まとめ
ここまで保育士の志望動機の書き方についてお伝えしてきました。
保育士は子どもの命を預かる責任重大な業務で、ハードな側面もあります。しかし、子どもたちの屈託のない笑顔や純粋さに元気をもらうような瞬間も多くあるでしょう。
幼いころから保育士を目指して努力を重ねてきた就活生が多いことと思います。
自分の夢の実現に向けて、自分の保育に対する思いと情熱が伝わる志望動機を作成するために本記事が少しでも役立っていれば幸いです。
就職エージェントneoを活用して就活をしよう!
- 「志望企業から内定をもらえるか不安…」
- 「選考対策のやり方がわからない…」
- 「もっと自分に合う企業ってあるのかな…?」
このように就活に関する悩みは人それぞれでしょう。
就職エージェントneoでは、専任のアドバイザーが個別面談を実施し、就活生1人ひとりの就活状況をお伺いした後に、状況にあったアドバイスの実施や希望や適性に合った企業の求人情報を紹介しています。
「志望企業の選考を突破するために、ES作成のアドバイスがほしい!」「自分の希望・適正に合う企業が知りたい…」など、少しでも就活に不安がある方は是非就職エージェントneoをご利用ください。