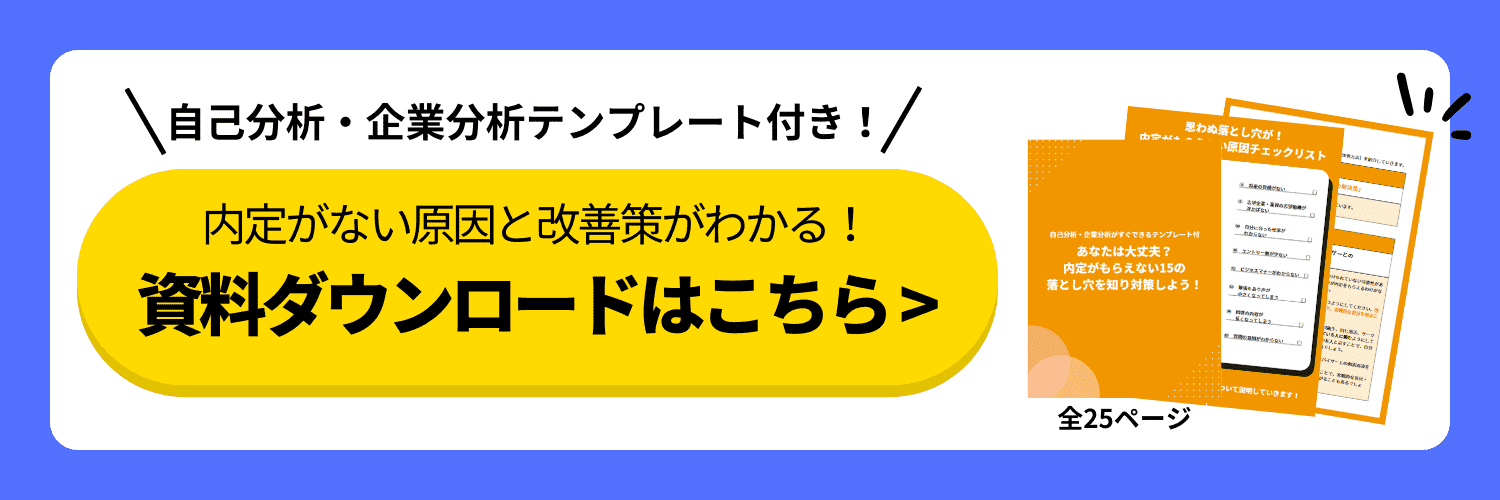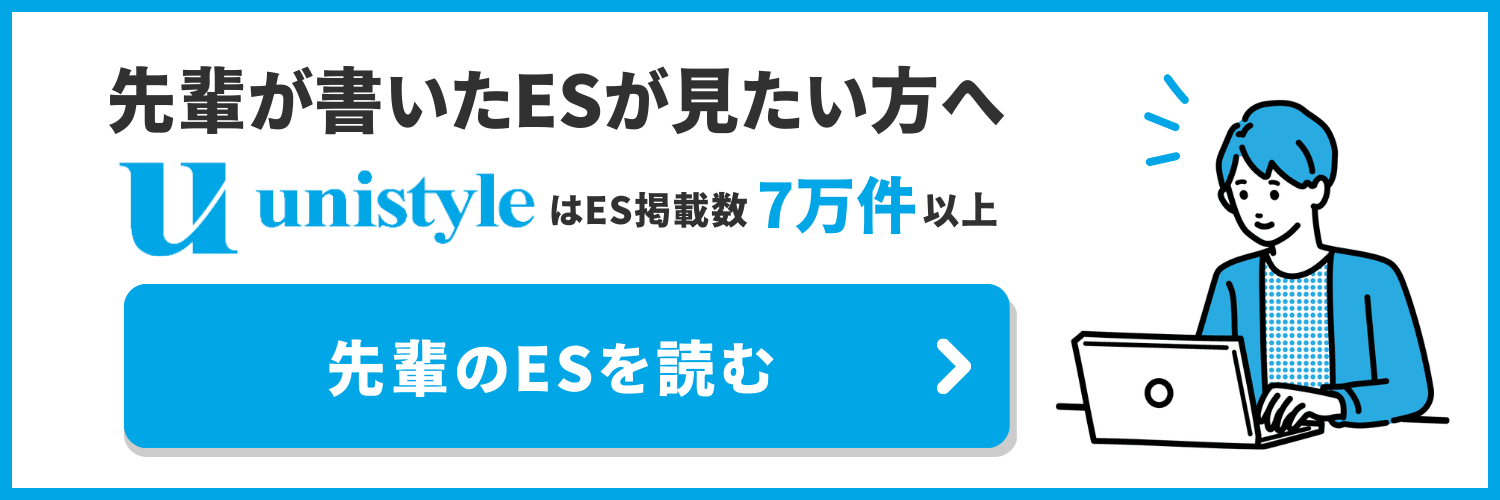●少子化の影響は受けているが、教育コンテンツのニーズは高まっているため直近の売上は復調しており、教育業界全体の市場は堅調。
●教育業界ではEdTech・STEAM教育・リカレント教育といったワードがトレンドなので抑えておくと良い。
教育業界と言うと[学校の先生」や[学習塾で働く人」などをイメージする就活生が多いのではないでしょうか?
教育業界は[これから少子化の影響を受けて市場規模が減少していく業界」だと言われていますが、実は日々新しいビジネスモデルが生み出されており、市場規模は拡大しています。
本記事では、教育業界の業界動向だけではなくビジネスモデルや主な職種の仕事内容、教育業界の求める人物像などをわかりやすく解説していきます。
教育業界での就職を考えている就活生は、教育業界の動向やトレンドを漏れなくキャッチアップするためにも、是非本記事を最後までチェックしてください。
教育業界とは?

教育業界というと、小学校などの初等教育、中学校・高校などの中等教育や、専門学校から大学・大学院などの高等教育での学習や受験などに関連するサービス、学習塾や予備校などをイメージする就活生が多いのではないでしょうか?
しかし教育業界では、上記の対象者向けのサービスだけではなく、社会人はもちろん乳幼児から高齢者まで全ての人を対象に[学ぶこと」に関する事業を展開しています。
教育業界に含まれる企業は、乳幼児から社会人までの公文式学習を実践している[KUMON]や、個別指導学習塾の[スクールIE」、幼児教室や子ども向け英会話スクールを運営している[やる気スイッチグループ]、そして多種多様な通信講座を提供している[ユーキャン]などが挙げられます。
教育業界の動向5選
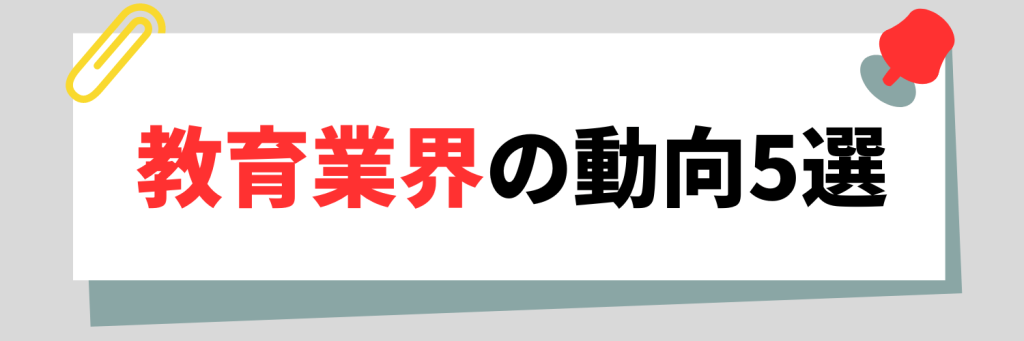
ここでは、少子高齢化が進む日本の教育業界の動向を、以下5つのトピックスに分けて紹介していきます。
少子高齢化に伴う影響
少子化が進んでいることから「教育業界って需要あるの?今後衰退していくのでは?」と心配している就活生もいるかもしれません。
たしかに少子化の影響により、乳幼児や学生の絶対数そのものが減少傾向にあることは事実です。
しかし参議院の調査室が発行している経済のプリズムコラムによると、1970年に2.4万円だった年間教育費は、2017年に37.1万円と約16倍に増えており、子ども1人当たりの年間教育費は年々増加していることがわかります。
また高齢化に伴い、定年後の自己啓発や各種講座(料理・お金・健康など)へのニーズが高まっている他、キャリアアップ・独立、再就職に向けたITスキルや各種資格・外国語検定の取得を目指す人も増加傾向にあります。
このように教育コンテンツのニーズが高まっていることから、直近の売上は復調しており教育業界全体の市場は堅調と言えるでしょう。
参照元:参議院|子どもの減少と相反する一人あたり教育費の増加
新学習指導要領の改訂
小学校では2020年度、中学校では2021年度、高等学校では2022年度から、新学習指導要領が改訂されました。
新学習指導要領とは文部科学省が定める教育課程(カリキュラム)の基準のことです。
新学習指導要領では[主体的・対話的で深い学び(アクティブラーニング)」の視点から、子どもたちの学習方法を変えることを重視しています。
アクティブラーニングとは、生徒が自分で考え、主体的・対話的に行動し、深く学ぶといった意味があり、学校における授業時間が削減された[ゆとり教育」では養いにくかった自ら社会的能力や経験、教養を身につけることを重要視している学習手法の1つです。
また、小学校では英語が必須科目になったり、プログラミング教育が導入されたり、社会の変化に対応した学びが実施されています。
特にプログラミングにおいては、国内外問わずIT化の需要が高まる中「2030年の日本は78.9万人ものIT人材が不足する」と言われていることから、将来のIT人材育成にむけ、プログラミング技術を取得するための授業が必修化されるようになりました。
大学入試制度の変化
2020年度(2021年1月)から、大学入試センター試験に代わり[大学入学共通テスト]が実施されるようになりました。
出題形式はセンター試験の時と変わらずマーク式であるものの、全体的に複数の資料を読み込んだ上で考えて解くような問題が多く、[思考力][判断力]を問う問題内容へと変化しています。
その中でも特に英語は、配点が以下のように大きく変わり、今までよりも高い英語力を求める内容に変更されています。
- センター試験:筆記(リーディング):200点/リスニング:50点
- 共通テスト:筆記(リーディング):100点/リスニング:100点
そのため学習塾や予備校などでは、上記のような変化に対応できる講師やテキストの準備が求められています。
オンラインを活用した非対面教育への対応
2020年に発生した新型コロナウイルスの影響で、学習塾などの教室といった『場』で指導をするモデルのビジネスでは売上が減少しました。
それに代わってオンライン授業などが拡大・一般化したことで、全員が同じ場に集まって授業を受けずとも、いつでも自分のペースで自分に必要な勉強ができるようになったため、最近では[オンライン通信教育サービス]や[eラーニング]の需要が増えています。
またビジネスの場も同様に、在宅勤務やリモートワークが一般化されたことで、オンラインを活用した研修への移行が加速しています。
これらの変化に対応するため昨今の教育業界では、非対面型のサービスの提供が求められるようになりました。
M&Aや業務提携による企業再編
近年、少子化の影響もあり、大手の学習塾や予備校などでM&Aや業務提携などの企業再編が進んでいます。具体的には、以下のような企業がM&Aを実施しました。
[Z会」が[栄光ゼミナール」を買収(2015年)
[代々木ゼミナール」が[サピックス」を買収(2016年)
このようにすでに教育事業を展開している企業が、提供できるサービスの幅を広げたり、新たな顧客の取り込みをおこなったりするためにM&Aや業務提携の実施を検討する企業が増えています。
教育業界の3つのトレンドワード
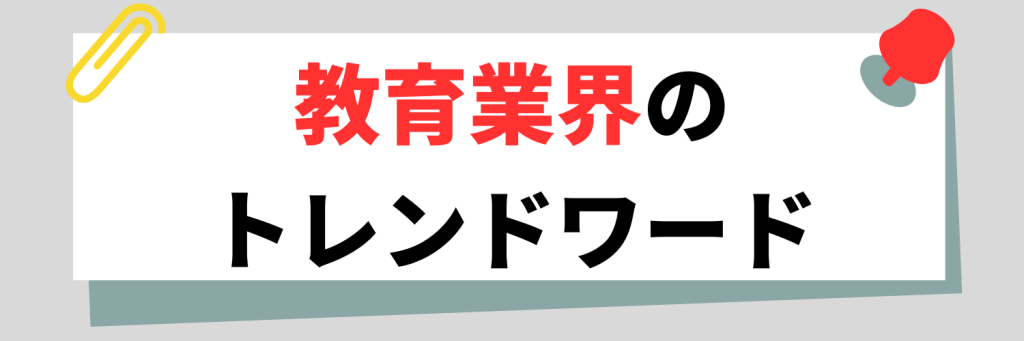
EdTech(エドテック)
EdTech(エドテック)とは[Education(教育)」と[Technology(技術)」を組み合わせた造語で、AIやインターネットなどのテクノロジーを用いて教育を支援する仕組みやサービスを指します。
EdTechには、生徒向けの教材や学習管理ツールなどの学習支援ツール、インターネット上で英会話やプログラミングなどを学習できるサービス、その他にも教師が活用できる授業支援システムなどがあります。
STEAM教育
STEM(ステム)とは、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)。芸術・リベラルアーツ(Arts)、数学(Mathematics)という5つの領域の頭文字を組み合わせた造語です。
STEM教育とは、上記の5つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念を指します。
STEAM教育では、日々の体験の中でさまざまな課題を見つけ、クリエイティブな発想で問題解決を創造・実現していくための手段を身につけることを目的としています。
リカレント教育
リカレント教育は、[学校教育からいったん離れたあとに、仕事で求められる能力を必要に応じて自分のタイミングで学び直すこと]です。
リカレント(recurrent)には、[繰り返す」・[循環する」といった意味があります。
国は社会人になっても生涯学び続けるリカレント教育を推進・支援しており、厚生労働省では、経済産業省・文部科学省などと連携して、学び直しのきっかけともなるキャリア相談や学びにかかる費用の支援などに取り組んでいます。
参照元:厚生労働省|リカレント教育
教育業界のビジネスモデル
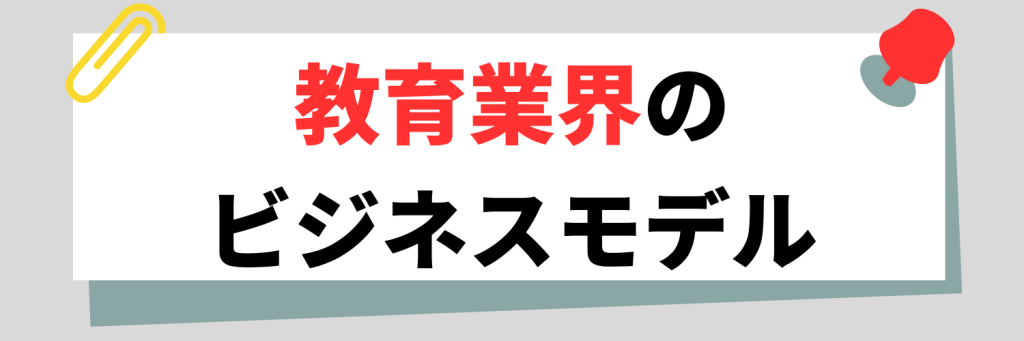
教育業界は、何かを学びたい・学びの機会を与えたいと考えている[受講者や企業]が、知識や情報を提供する[学校教育機関・学習塾・語学教室・カルチャー教室・人材育成企業]を利用することで成り立っています。
このような教育業界のサービスは対象別に[学生向けのサービス]と[社会人・企業向けのサービス]の2つに分けられます。
学生向けのサービスは、主に学習塾や予備校、英会話や資格取得のためのカルチャー教室など、スクール型のものがあり、社会人・企業向けのサービスは、スキルアップ・自己啓発に向けた研修などがあります。
以下ではそれぞれどのようなサービスがあるのかを紹介しますので、確認してみてください。
学習塾・予備校
学習塾・予備校は、小学生・中学生・高校生を対象に学習指導をおこなう場で、大手チェーンから個人運営の塾まで規模はさまざまです。
学習塾・予備校を運営する企業には、[ナガセ(東進ハイスクールや四谷大塚)][公文教育研究会(KUMON)][栄光(栄光ゼミナール)][学研ホールディングス(学研教室)]が挙げられます。
また、学習塾・予備校には[個別指導」と[集団指導」があり、それぞれ教え方は異なります。以下にてそれぞれの違いを表でまとめたので抑えておきましょう。
・生徒1~3人を担当
・基本、1人ひとりの学びたい内容に沿って教育
・学生やアルバイトのマネジメント業務もある
・多数の生徒を集めて授業をおこなう
・決められた時間やカリキュラムでおこなわれる
・生徒が飽きないようなプレゼン力が必要
個別指導か集団指導かで教え方も変わってきます。企業によっても雰囲気や特徴が変わってくるので企業研究もっておこなっていきましょう。
語学教室
子供から大人まで幅広い層を対象に語学指導をおこなっています。指導する外国語は、英語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語など多岐にわたり、外国人向けに日本語を指導する場合もあります。
語学教室を運営する企業には、[ベルリッツ・ジャパン(Berlitz)][イーオンホールディングス(イーオン)][ECC(ECCジュニア・ECC外語学院)]が挙げられます。
言語の理解には、文化や風習などの背景も密接に関わるため、教える内容は語学だけに留まりません。国や文化にも目を向けて情報収集をしていく必要があります。
カルチャー教室
カルチャー教室とは、絵画やスポーツ、音楽、パソコン、料理などを教える教室のことを指します。ピアノやサッカー、スイミングスクールといった習い事が該当します。
上記にて紹介した学習塾や語学教室もカルチャー教室の一部に当たりますが、メジャーな存在のため抜粋して説明しています。
最近では、学校教育でも取り入れられているプログラミングを学ぶ教室や大人向けのスキルアップに向けた教室、小学校受験のための英才教育塾もできています。
カルチャー教室を運営する企業には、[ヒューマンホールディングス(ヒューマンアカデミー)]、[TAC(資格の学校TAC)][ 読売・日本テレビ文化センター(よみカル)]が挙げられます。その他、個人で開業し自宅で教室を開くケースもあるようです。
人材育成企業
人材育成企業では、企業を中心に新入社員向けにビジネスマナーを教える研修を代行したり、キャリアアップのための講習をしたりしています。
これらの研修では、将来必要とされる能力の開発を見込んでの研修や講座を求められることもあり、場合によっては、短期(1~2年)と中期(3~5年)の人材育成戦略を考える必要があります。
人材育成をおこなっている企業は、[リクルートマネジメントソリューションズ][リンクアンドモチベーション][グロービス]などが挙げられます。
教育業界に関わる職種
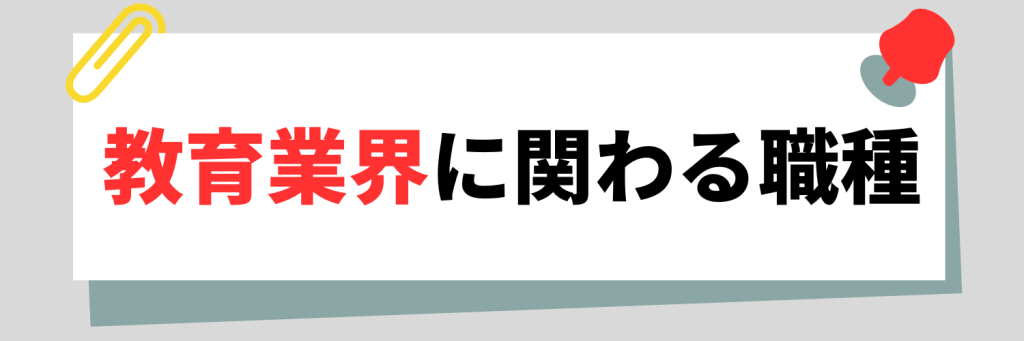
教育業界には[講師]という職種以外にも、幅広い職種が関わっています。以下では教育業界の主な職種の仕事内容を紹介します。
学生時代に学習塾や予備校に通った経験がある就活生は、当時のことを振り返りながら読み進めると、仕事内容のイメージが持ちやすくなるでしょう。
講師
講師は教育業界ならではの職種の1つで、教育現場の最前線に立ち、受講者の学力や目的、適性に応じて授業や講義を実施します。
授業がない時には、試験問題の作成・事務作業・生徒の質問や悩み、保護者への対応・校舎の運営などもおこないます。
講師は学校の教員と異なり、教員免許などは必要ありません。
サポートスタッフ(試験問題研究・編集制作)
生徒・講師にとって通いやすい・働きやすい環境を整えることが事務の役割です。
具体的には、教室の清掃や授業の準備、書類作成、データ入力、お問い合わせ対応など、学びの場の運営に必要な業務を担当しています。
また予備校には事務とは別に、学生をサポートするチューターという職種があります。チューターは主に大学生が役割を担っており、学生の学習サポートや進路相談、日常生活の悩み相談を受けています。
営業・マーケティング
営業・マーケティングは、ユーザーに対して自社サービスの活用・導入を提案する職種で、教育業界において欠かせない職種の1つです。
例えば学生向けの教材を商材としている企業の営業であれば、学校や学習塾・予備校に対して、その商材を活用してもらえるようにアプローチをおこないます。
法人向けの研修サービスを提供している企業の営業であれば、クライアント先企業のニーズを満たした教育コンテンツの導入を提案するでしょう。
このように企業が扱う商材によって営業先は異なります。
そしてマーケティングでは、集客に向けた広報宣伝物の企画や制作、広告運用などをおこないます。その他にもパンフレットやホームページの制作などクリエイティブな仕事も担当します。
教育業界に向いている人とは?
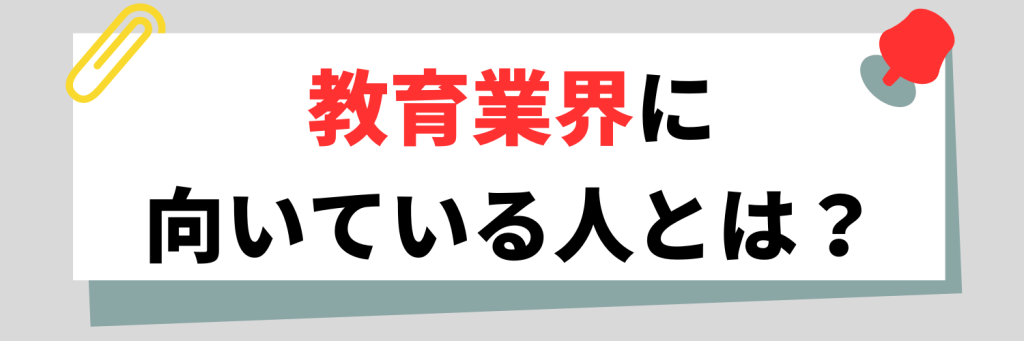
教育業界では、乳幼児から高齢者まで様々な個人・集団に対して、教育を提供しています。その際、生徒はもちろんですが生徒の保護者や他の講師など職場の人とも関わる機会が多くあります。
特に生徒と接する際は、日頃から信頼関係を構築するために生徒1人ひとりと向き合い、それぞれにあった個別のアドバイスをしたり、サポートしたりすることが求められます。
中には学習に意欲的ではなかったり授業についていけず苦戦していたりする生徒もいるでしょう。しかしそのような生徒に対しても他の生徒同様、寄り添いながら根気強く教えられる熱意があることも非常に重要です。
つまり教育業界は、いろいろな人とコミュニケーションを取りながら、誰かのために何か行動をすることにやりがいや喜びを感じる人などに向いていると言えるでしょう。
また教育業界は、学習指導要領に変更があったり、試験情報や試験の傾向が毎年アップデートされたりと、日々環境が変化しています。
そのため自らの情報をアップデートするための情報収集をするだけでなく、自分自身も勉強し続けられる人も教育業界に向いていると言えます。
教育業界で評価される志望動機の書き方が知りたい人は以下の記事を是非参考にしてください。
教育業界の優良企業とは?
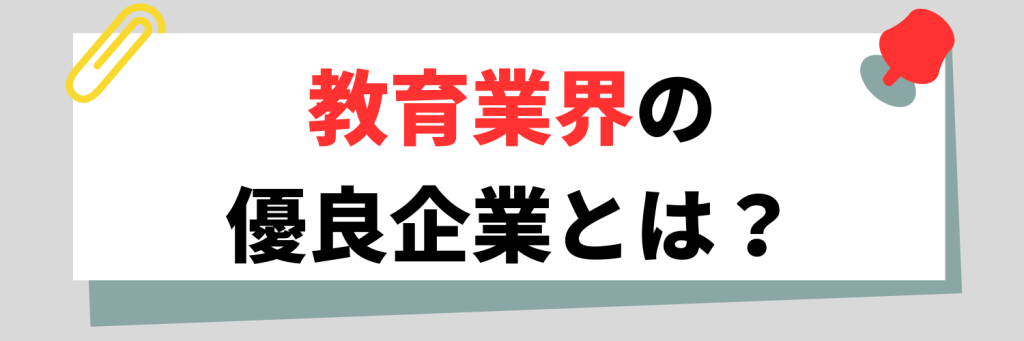
以下では教育業界の売上が高い上位3つの企業を紹介します。
売上は企業の財務力・ビジネスの規模を表しています。つまり売上が高い企業はおこなっているビジネスの規模が大きいということです。
業界動向サーチが公開している売上高ランキングによると、2022年-2023年の教育業界売上高トップはベネッセHD、2位が学研HD、3位がヒューマンHDという結果でした。
それぞれ簡単に3社の企業を紹介します。
株式会社ベネッセホールディングス
株式会社ベネッセホールディングスは、子会社37社および関連会社8社で構成されており、各社は[国内教育][Kids&Family][介護・保育]という3つの事業セグメントを中心に事業を展開しています。
具体的には、ベネッセコーポレーションや東京個別指導学院などの企業が教育事業をおこなっています。
ベネッセコーポレーションは、幼児向け通信教育講座[こどもちゃれんじ]や小学生から高校生を対象とした通信教育講座[進研ゼミ]、高校生を対象とした大学入試模擬試験[進研模試]などを提供しており、また東京個別指導学院は個別指導塾・学習塾を運営しています。
株式会社学研ホールディングス
株式会社学研ホールディングスは、連結子会社75社・非連結子会社18社・関連会社14社で構成されており、大きく[教育分野]と[医療福祉分野]の2つの事業を中心に展開しています。
[教育分野]はさらに[教室・塾事業][出版コンテンツ事業][園・学校事業]の3つにわけることができます。
[教室・塾事業]に含まれる企業は、教育・塾事業を運営している[市進ホールディングス][学研塾ホールディングス][早稲田スクール]などです。これらの企業では幼児から中学生を対象にした学研塾・進学塾を運営しています。
[出版コンテンツ事業]では学習参考書や教材の開発・販売などを、そして[園・学校事業]では教科書・教師用指導所などの製作・販売をおこなっているなど、幅広く事業を展開しています。
ヒューマンホールディングス株式会社
ヒューマンホールディングス株式会社は、持株会社のため子会社に対する経営指導や管理などをおこなっています。
教育事業を展開している子会社は、[ヒューマンアカデミー株式会社][ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社][ヒュー万スターチャイルド株式会社]などです。
これらの企業では、教育現場と企業・行政を繋いで実践教育を実現するための[社会人教育]や世界で活躍できる人材を育成する[国際人教育]などに力をいれた事業を展開しています。
まとめ
本記事を通して、教育業界の業界動向やビジネスモデル、仕事内容について理解を深めることはできましたでしょうか?
就活で自分が志望している業界の選考を突破するためには、業界に関連する情報を集め、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。
中でも業界研究をする際は、[その業界では今どのような動向があるのか?」[どういう市場状況なのか?」[どのような人材が求められているのか?」といったことまで調べられると、効果的な自己PRや志望動機を作成することができるでしょう。
業界研究をさらに詳しくおこなう方法は、下記の記事を是非参考にしてください!
就職エージェントneoを活用して効率的に就活をしよう!
「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして最も歴史がある就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有しており、累計紹介企業数10,000社、内定支援実績45,000件を誇ります。
10年後を見据えた企業探しや面接後の個別フィードバックなどをおこなっており、Googleの口コミ評価は4.5と高水準です。
その他、いきなり責任者面接を受けられる特別推薦枠や、書類選考・一次選考が免除になる求人の取り扱いもあることから、時期によっては最速1日で内定が出る場合もあります。
就職エージェントneoのサービスは、就活生1人ひとりに専任のアドバイザーが付き、就活相談や選考対策などもおこなっているため、就活出遅れ組の学生にもオススメのサービスです。
「面接の練習をしたことがなくて本番が不安…」「自己分析のやり方を調べてもピンとこない…」といった就活生は、是非一度私たちにご相談ください。